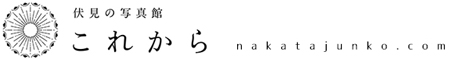子どもに関わる大人として学んだ、子どもアドボカシーのこと

こんにちは、館主の中田です。
とてもとてもご無沙汰の雑記です。
今日は、ちょっとお伝えしたい最近の出来事がありまして。
この度、「子どもアドボカシー学会」が主催する「子どもアドボカシー基礎講座」を受講し、無事に修了認定をいただきました。
「子どもアドボカシー」とは…
子どもが自分の思いや考えを自ら話せるように支援したり、必要に応じて、本人の依頼や同意のもとでその声を代弁したりすることです。
そして、子どもの側に立って、必要な支援や働きかけを行う人を「子どもアドボケイト」と言います。
今年のはじめ、福岡で保育園を運営している友人と久し振りに会う機会があり、友人が子どもアドボカシーに関わる活動をしていることを知りました。
「子どもアドボカシー」「子どもアドボケイト」という言葉を知ったのは、そのときが初めて。
ですが、すぐに強く惹かれるものがありました。
わたしはこれまでの経験から、
「子どもに関わる大人は、親や先生だけじゃなくていい。親でも先生でもない“第三の大人”だから果たせる役割がある」
と感じながら生きてきました。
また、日々の撮影などを通じて子どもと接することも少なくない中で実は、子どもとの関わり方に自信がないな…という気持ちもずっと持っていました。
自分の言葉や態度が、知らず知らずのうちに子どもの尊厳を傷つけたり、子どもの「声」を奪っているかもしれないことが怖かったのです。
そんな思いへのひとつの答えとして、子どもアドボカシーを学ぶことが必要だと感じました。
独学で本を読んで勉強することも考えましたが、わたしの場合は「対話を通じて理解を深めたい」「学びの土台をしっかり築きたい」との思いから、学会主催の講義形式の基礎講座を選びました。
受講前は、撮影の仕事とは直接関係ないかもしれない、と思っていましたが、今は、撮影の仕事に止まらず、自分の生き方に深く関わる学びだったと感じています。
子どもの権利条約について無知だったことや、無意識の差別や偏見だらけだったこれまでの自分を大いに反省しました。
アドボカシーは子どもだけのためのものではありません。
子どもも大人も、誰にとっても「自分の思いが尊重されること」が当たり前になり、それをみんなで支える社会になることを願っています。
そして、写真の仕事や地域で関わってくださるみなさんと、より一層安心できる関係でいられるように、問い続け、学び続けたいと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いします。
- カテゴリー
- 雑記